★「教える」を極力、短くする
前回は、学校は、子どもたちが「自立して学ぶ力」を育む必要があるというお話をしました。
今回は、では、どうすれば学校教育でこのような力を育てることができるのかについて考えてみます。
私は、そのカギは、「自学力」「自己調整力」といった力を育む授業と、
対話や体験学習を通して「最適解を探る」といった力を育てる授業への転換にあると思っています。

とはいえ、今の教育課程には制限が多く、すぐに理想的な授業をめざすのは難しいでしょう。
できることから考えるとすれば、まずは、教師が一方的に教えている時間を減らすことです。
たとえば、一単位授業なら、教師が教えている時間を10分から15分くらいに抑えます。
残り、30分から35分を、自学や対話の活動に充てます。
または、10単元の授業なら、最初の3時間を教師が教え、基本的な知識や技能を学ぶ時間に使い、残りの7時間を自学や対話に充てるのです。
これからの社会では、知識、技能と同様に、思考力、判断力、表現力も常にリニューアルをしていくことが求められます。
そして、それは、もはや教えてもらうことを待っていては、時代の変化に追いつけなくなってしまうのです。
自分をアップデートさせることのできる力がなければ、今後の社会を生き抜いていくことが難しくなるのです。
そして、そもそもなんですが、教師が一方的に教える授業というのはあまりに弊害が大きいからです。
このことについては、前回のnoteで触れていますので、そちらをお読みください。
https://note.com/embed/notes/n1556333c635b
★教師はコーチングの知識とスキルが必要になる
あと、教師の役割の転換も必要でしょう。
これまで通り専門的な知識や教授法の習得は欠かせません。
しかし、同時に、コーチングの知識とスキルを身につける必要があります。
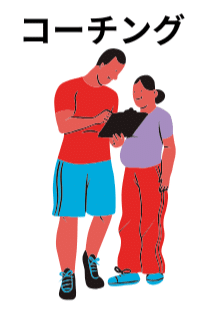
生徒の学びの伴走者として、問いかけや対話を通じて学びを促す、より高度なスキルを習得していくことが求められます。
さらに、授業時間、時間割に柔軟性を持たせることも今後の課題です。
画一的な45分、50分といった授業だけでなく、学ぶ内容によって90分、1時間連続といった柔軟に構成できるシステムも必要でしょう。
あと、道徳や特別活動については、変える必要はありません。
普遍的な価値や協働意識を学ぶという観点からも、今後、ますます必要とされるはずですから、継続、充実させてほしいです。
★ストレスを感じなければアップデートはできない
話は逸れますが、私はよくタクシーを利用します。
今は、流しのタクシーがなかなか拾えないので、ほとんどアプリでタクシーを手配しています。
このアプリ、最初は恐る恐るでしたが、今は慣れてしまって、こんな便利なものはないと思えるまでになりました。
なにせ、いつつかまえられるかどうかわからない流しのタクシーを待つ必要がありません。
また、クレカと連動しているので、現金のやり取りをしなくてすみます。
この便利なアプリ、私と同世代(60代)は使うことができない人も多いのです。
聞いてみると、
「クレジットと紐づけるのはいや」
「目的地を入力するのがめんどう」
「アプリは信用できない」
いろんな言い訳をしてきますが、そもそも面倒なだけです。
自分が今できることを、リニューアル、アップデートさせるって、結構面倒なことなのです。

しかし、その「面倒くさい」を乗り越えなければ、自分をアップデートさせることはできないのです。
たとえば、筋トレに例えると、トレーニングは面倒ですが、筋肉はトレーニングによって繊維が破壊された後、再生され、以前よりも強度を増していきます。
同様に、脳も新たなことにチャレンジすることで、ストレスを感じながらも、その後は機能が高まっていくはずです。
★変わることのできる力
これはアプリを使って、タクシーを呼ぶ側だけでなく、タクシーの運転手さんにも言えることです。
先日、アプリを使ってタクシーに乗りました。
運転手さんは、御年82歳。
私より20歳も年上の方です。
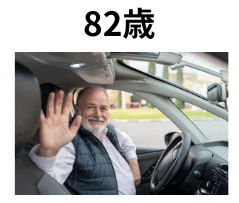
運転席には、複数の液晶パネルが設置されています。
複数のアプリの操作をこのパネルで行うわけです。
80歳というお年で、このパネルの操作はできるのか。
失礼ながら、そういった疑問が頭をもたげました。
そこで、失礼を承知でお聞きしてみました。
「パネルの操作、大変じゃないですか」
すると、運転手さんは
「慣れるまでは大変でしたが、これが使えないと仕事にならないので、必死で覚えましたよ」
「最初は無理だと思っていましたが、やってみるとできるものですね」
そういって笑っていました。
続けて、次のように話してくれました。
「でも、最初から難しいからって、使う前からあきらめて辞めていった運転手もたくさんいるよ」
「82歳の私でもできるのに、60歳の運転手で無理って言って辞めた人もいるんですよ。食わず嫌いは損だよね」
おそらく、自分自身のリニューアル、アップデートに対する耐性がなかったのでしょう。
変わることに慣れていなかった。
または、変わることに係る能力が足りなかった。
そういうことです。
幸いにも私たち世代は、今まで、大きな変化に対応しなくても、何とか生きてこられたのです。
仕事上必要な基本的な知識とか、技術を一端学んでしまえば、退職までやってこられたのです。
しかし、これからの世代はそうはいかないでしょう。
現代社会で、職業人として成功するためには、生涯にわたって学び続け、アップデートしていくことのできる力が不可欠だと言い切っていいでしょう。
ということで、教育現場の先生方も大変だと思いますが、一歩ずつでも改革を進め、子どもたちが社会に出て生き抜いていける力を育んでいただきたい、そう切に思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
よろしければ下記のサイトもご覧ください。
●無料メルマガ登録:https://my142p.com/p/r/A78JnRVw
●note:https://note.com/rosy_stork651/
●音声配信stand.fm:https://stand.fm/channels/66bc4832dc616cb3f4a66474
●X(旧Twitter):https://x.com/gracia4041
●Instagram:https://www.instagram.com/gracia_okane/
.png)

