★「驚異的」としか言いようのない社会変化
現在、文科省は
次期学習指導要領の改定に向けて
専門家を交えて議論を進めているところです。
その議論の内容を見てみると、
今後の社会変化を見据えて、
かなり踏み込んでいる印象があります。
ただ、参加メンバーが、
大学教授などの専門家の方々が多いためか、
一般の方には議論の中身を
理解するのが難しいところがあります。
といくおとで今回は、その議論の内容を加味し、
今後の学校教育について、
私の考える方向性を述べさせていただきます。
まず、現代の学校教育は、大きな転換期を迎えています。
これは確かです。
みなさんも同様に感じていると思います。
まず、社会変化のスピードが半端じゃありません。
スマホは、わずか数年で、
世界中の人々の生活に不可欠な存在となりました。
かつて経済の中心は、
家電メーカーや自動車メーカー企業でしたが、
今や、Amazon、Googleといった
新しいビジネスモデルを持つ企業が
世界経済を回しています。
働き方も、 リモートワークやフリーランス、
副業・兼業と多様化し、それが一般化しつつあります。
終身雇用の時代から、
スキルを高めながら、複数の会社を経験していく
キャリア形成が重要視される時代になってきています。
そして、未来を劇的に変化させるといわれる
AIの進化については、
驚異的としか言いようがありません。
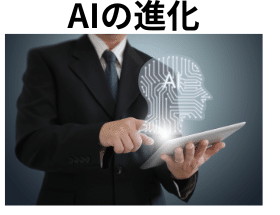
★まるで「修行」のような「一斉授業」
こんな時代において、
今後、子どもたちが必要となるスキルとは何なのか。
その答えはそれほど難しいものではありません。
今後、子どもたちに必要な能力、
スキルとは端的に言えば、
常に知識やスキルをリニューアルさせることのできる力です。
もっとシンプルに言えば、
自分をアップデートさせることのできる力です。
実際、現行の学習指導要領も
そのことをかなり強調しているんです。
すべては「主体的・対話的で深い学び」、
このめざす授業像に集約されています。
なので、この理念が体現された授業が
全国隅々で展開されていれば問題ありません。
しかし、残念ながら、多くの学校では、
未だに、教師が一方的に知識を「教え」、
生徒がそれを「覚える」という従来の授業スタイルから抜け出せていません。
文科省が、尽力し、
生徒一人に一台端末を配布し、
「個別最適な学び」「協働的な学び」を
提唱しているにもかかわらず、
それを最大限活用し、実践している学校は限定的です。
なぜかと言いますと、今のカリキュラムでは、
覚えなければならない知識が膨大で、
それを覚えさせることだけに時間が使われてしまうからです。
また、一人の教師が抱える生徒数が多すぎるのです。
これだけの知識を、これだけの数の生徒に
「教える」となってくると、
必然的に一斉授業になってしまうのです。
一斉授業で探究心や
自己調整力なんて育つわけがありません。
それどころか、この一斉授業、他にも弊害も多いのです。
まず、一斉での学習ですから、
個々の生徒の学力に合わせた学習ができません。
ですので、生徒間の学力差は広がっていきます。
さらに言えば、
一斉授業は、教師、生徒双方にとって大きな負担になります。
例えば、理解力の高い生徒にとっては
「たいくつ」ですし、
学力的に厳しい子にとっては、
「ちんぷんかんぷん」というのが一斉授業です。
そんな一斉授業の中で、
毎時間同じ席、同じ姿勢で
ひたすら教師の話を聞き、ノートを取る。
まるで修行です。
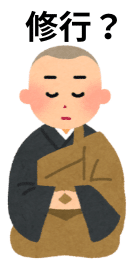
そんな授業を、1日6時間も受けなくてはならない、
子どもたちの精神的、体力的な負担は
かなりのものだと想像できますよね。
だからと言って、
教師側だけに責任があるのかと言えばそうでなくて、
教師が授業を工夫しようにも、
使う教科書はどれもほぼ同じ規格です。
授業時間や時間割も固定されているので、
発展的・独創的な授業にしようとしても限界があります。
ですので、文科省は、
現場の努力だけに頼るのではなく、
その根源となっている「学習指導要領」を
大胆に進化させる意気込みがほしいのです。
そうでなければ、
子どもたちが必要とするスキルを習得できないまま社会に出てしまうことになり、
将来的にかなりの苦労を強いられます。
★リアルな社会では
さて、話は脱線しますが、
ここで、少し事例を交えてみます。
私が仕事を通じて知り合った方ですが、
仮にBさんとしておきましょう。
Bさんは不動産会社を経営していて現在40代です。
Bさんは、東京の国立大学を卒業し、
国内大手の不動産会社に就職しました。
入社後、宅地建物取引士の資格の重要性を感じ、
独学で資格を取得しました。
厳しい受験競争をくぐり抜けてきたBさんにとって、
資格取得はそれほど難しいものではありませんでしたし、
資格取得後も、わからないことがあれば、
書籍やネットを活用し、
効率的に仕事を進めることもできたようです。
ただし、これだけで一流になれるわけではありません。
Bさんは実務を通して、
先輩や顧客、投資家と対話する中で、
乗り越えがたい課題に直面します。
例えば、土地活用の提案をする際に、
単に収益計算するだけでなく、
将来に向けて、
より高い価値を提供できるかどうか
様々な角度から分析し提案していくわけです。
この段階で、
新たな知識やスキルの
リニューアルが必要になりますし、
何よりも、創造力が求められます。

そして、仮にいい提案ができたとして、
その提案の良さを顧客に伝え、
納得してもらうための表現力も要求されてきます。
さらに、その案を受け入れてもらうためには、
そもそも、顧客と信頼関係が
構築されていることが前提となります。
つまり、仕事の最終段階においては、
AIやマニュアルでは決して導き出せない
高度なスキルや、ビジネスの「法則」を会得していく必要に迫られたそうです。
★社会に出てからでは遅い
ここまでが、Bさんの事例です。
私が何を言いたいのか、
教員の皆さんならおわかりですよね。
Bさんが、仕事の壁を乗り越えるために、
最終的に、必要に迫られたスキルはというと、
思考力・判断力・表現力ですよ。
Bさんは、基本的な知識・スキルの習得は、
「自立して学ぶ力」が備わっていたおかげで、
何とか仕事の初期段階を越えられたわけですが、
ただし、その先の、
問いを立て、対話を通じて、
新たな価値を創造する力が備わるまでには、
かなりの時間と経験を要したということで、
Bさんが、自信が持てるようになったのは、
入社して10年以上経った頃だったそうです。
Bさんは今は独立し、不動産会社を開業しています。

いかがでしょうか。
Bさんの事例を通して、
学校がサポートすべき
生徒の学習スキルがイメージできたのではないでしょうか。
もちろんこういった力は、
実際に社会人になって、
実務を通して学ぶものだというのもだという意見も間違いではありません。
しかし、学校教育で
その疑似体験をするくらいでも、
子どもたちの将来は大分違ってくるはずだと私は思っています。
ということで、
次回は、これらの力を育むためには
学習指導要領の改善が必要なのかについてお話しします。
最後までお読みいただきありがとうございます。
よろしければ下記のサイトもご覧ください。
●無料メルマガ登録:https://my142p.com/p/r/A78JnRVw
●note:https://note.com/rosy_stork651/
●音声配信stand.fm:https://stand.fm/channels/66bc4832dc616cb3f4a66474
●X(旧Twitter):https://x.com/gracia4041
●Instagram:https://www.instagram.com/gracia_okane/
.png)

